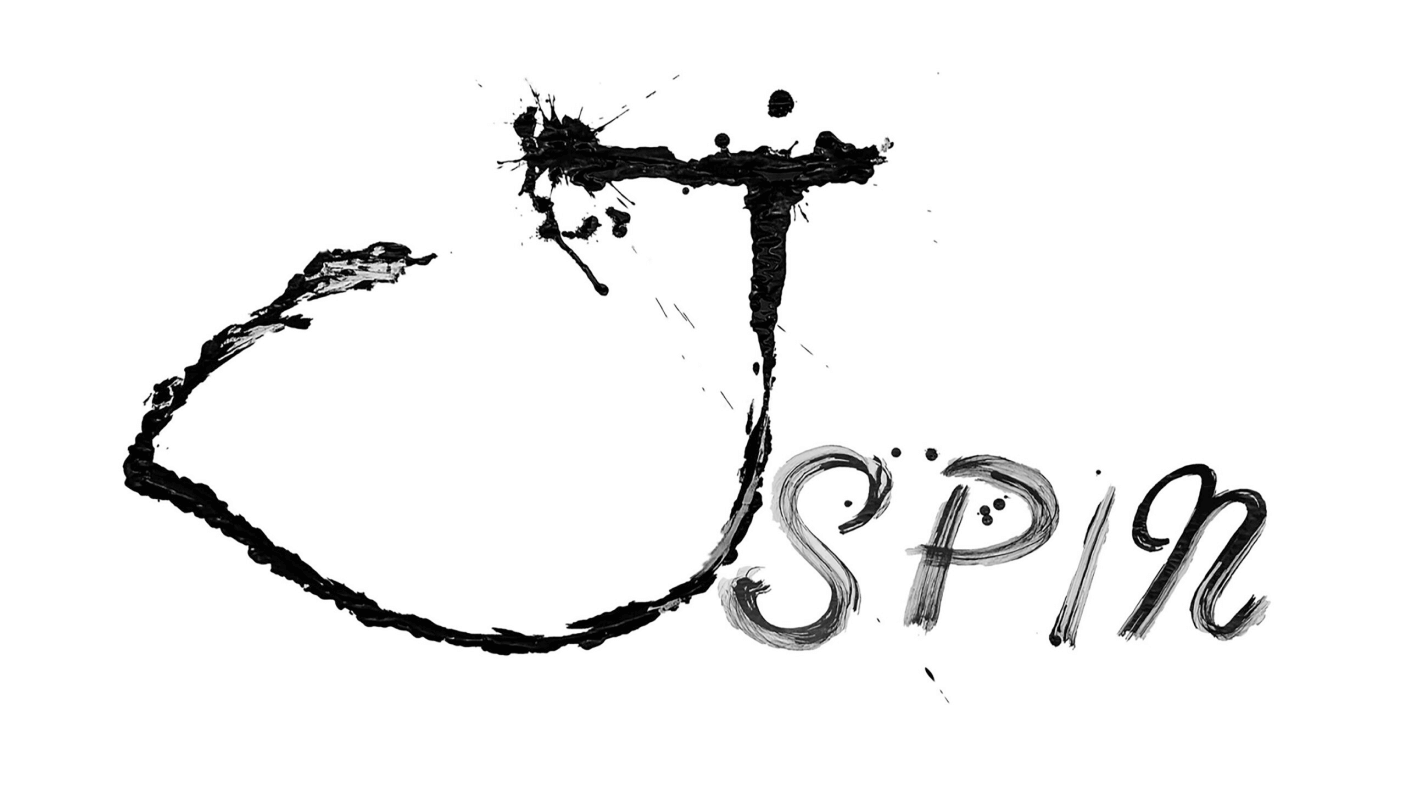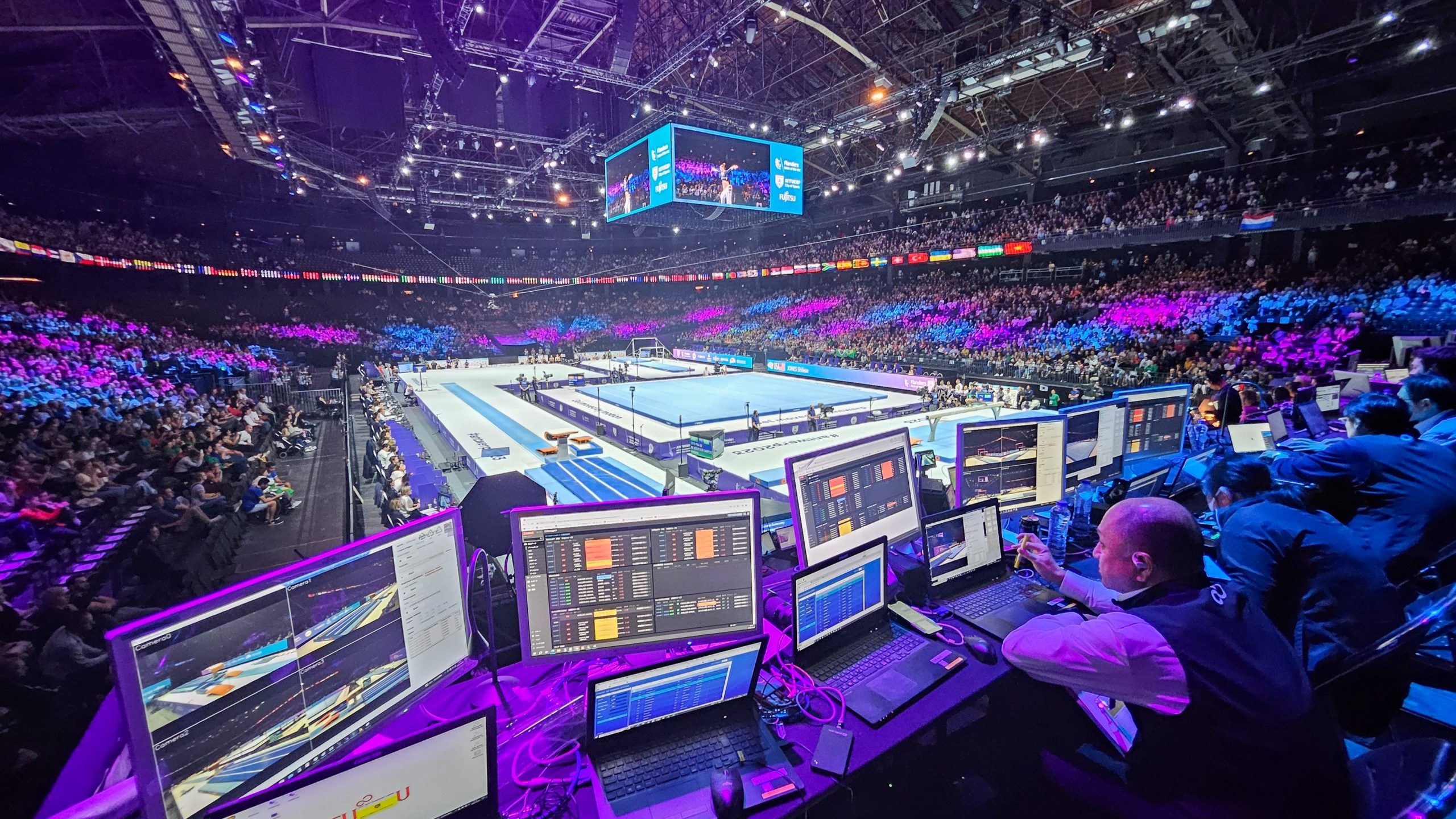「年間2000人」——この数字を初めて聞いたとき、私は言葉を失った。ベトナムで毎年溺死する子どもの数である。西太平洋地域において、ベトナムは水難事故による児童死亡率が最も高い国の一つとされている。特に0歳から14歳の子どもの溺死率は、先進国の約10倍に達しているのが現状だ。
2019年8月にベトナム進出し、2020年にFuji Swimming Clubの1号店をハノイにオープンしてから、今年で5年目となった。継続的な泳力検定会の実施などを通じて、年々、日本式スイミングレッスンに興味を持ってもらえる方も増え、多くの子ども達に泳ぎを教えることができるようになった。(参考:水泳の楽しさを伝えることで、ベトナムの水泳普及に挑む(エスアンドエフ 鮎澤貴孝) - JSPIN)
しかし、水泳を習えるのはレッスン代を支払える家庭に限られる。ベトナムでスイミングクラブを運営する中で、自分の身を守るための水難事故から自分を守る技術を習得する機会は、平等に得られるようにするべきという思いが強くなっていった。そこで、5周年を機に溺水防止イベントを開催することにした。
経済格差が生む「泳げない子」の現実
ベトナムの水泳環境は、日本とは大きく異なる。都市部では市民プールやプール付きマンションも存在し、希望すれば水泳を習う機会はある。しかし、レッスン料は12回1,200,000~1,500,000VND(日本円に換算すると約7,200~9,000円)が一般的だ。平均所得が日本の7分の1以下のベトナムにおいて、これは決して安い金額ではない。
結果として、水泳は中高所得者の家庭が中心の習いごとになっている。一方で、地方や低所得世帯の子どもたちは、泳ぎ方を学ぶ機会がないまま水辺で遊び、事故に巻き込まれるケースが後を絶たない。
この格差こそが、ベトナムの水難事故の根本的な原因の一つなのである。
日本の強みを活かした「泳げない子をなくそうプロジェクト」
私たちが日本国内で運営するサギヌマスイミングクラブでは、2013年から「地域から泳げない子をゼロに!」をスローガンとして、無料水泳教室を開催してきた。この取り組みの背景には、「水泳はすべての子どもが身につけるべき生存技術である」という強い信念がある。
日本の学校教育における水泳授業は、実は世界的に見て非常に珍しい取り組みだ。プールを持つ学校が多数存在し、体育の授業として水泳が組み込まれている国は、先進国でも限られている。この日本独自の教育システムが、日本を競泳大国として支える基盤となっているのは間違いない。
世界溺水防止デーに込めた想い
国連が世界溺水防止デーと定めた7月25日。2025年のスローガンは「その数秒で命は救える」だった。まさにこの日に合わせて、私たちはベトナム・ダナン市で初めての溺水防止イベントを開催することを決意した。

「誰もが平等に水難事故防止の知識や技術を身につけられるように」—この理念に共感してくれたのが、2つのベトナム企業(Yêu Bơi Lội、OKB Consulting Vietnam Co.,Ltd.)だった。Yêu Bơi Lộiは水泳動画配信に関するベトナム最大級のYouTubeチャンネル管理に加え、イベント開催や水泳道具の販売を行っている会社であり、水泳の普及という目的に合致して協力いただいた。また、OKB Consulting Vietnam Co., Ltd.は大垣共立銀行の設立によるベトナムでのコンサルティング会社であり、日本式スイミングによりベトナムで水泳の普及を目指す理念に共感いただいた。彼らの協力により、参加費が完全無料でのイベント開催が実現した。
21名の子どもたちが教えてくれたこと
イベント当日は5歳から12歳まで21名の子どもたちが参加した。すでに泳げる子から全く水に慣れていない子まで、参加者の水泳レベルは実に様々だった。
通常の水泳レッスンとは異なり、このイベントでは以下に重点を置いた:
- 水辺の危険性についての座学
- 海や川で遊ぶ時の注意点
- 万が一溺れそうになった時の対処法
- 実技を通じた自己救助技術の習得
子どもたちの真剣な眼差しを見ていると、彼らが単に「泳ぎ方」を学んでいるのではなく、「命の守り方」を学んでいることを実感した。

現地からの反響と今後への期待
イベント終了後、近隣の保育園の園長先生からは「子どもたちが興味を持ちながら、危険の認識から水辺での適切な対応まで、生活に欠かせないスキルを身につける有意義な学習体験ができました」という声をいただいた。
さらに、ダナン市のテレビ局が取材に入り、イベントの様子がテレビ放映されたことで、地域社会からの注目度も高まった。これは、ベトナム社会全体がこの問題に対して高い関心を持っていることの証左でもある。
アジア展開への野望と日本の役割
現在、私たちの取り組みはベトナムのダナンで展開している。しかし、水難事故の問題はベトナムだけに留まらない。タイ、マレーシア、インドネシアなど、東南アジア諸国の多くが同様の課題を抱えている。
日本の水泳教育システムの強みは、単に水泳の技術指導だけでなく、「心配り」や「整理整頓」といった人格形成の要素も含んだ総合的なアプローチにある。この日本式指導法を、アジア各国の実情に合わせてカスタマイズし、展開していくことが私たちの次なる目標だ。
特に、学校教育に水泳が普及していないアジア諸国において、民間スイミングクラブが果たす役割は極めて大きい。私たちが培ってきた1973年からの指導実績を活かし、アジア全体の水難事故削減に貢献していきたい。
データが示す成果
S&F VIETNAMとして、ベトナム現地で行ってきた水泳検定の取り組みの成果を数字で整理すると、2020年から開催し、都市はハノイ、ホーチミン、ダナンの3都市。2025年8月3日の開催で7回目。開催した水泳検定には7回で延べ345名が合格している。しかし、年間2,000人という溺死者数を考えると、まだまだ道のりは長い。
成果測定の方法として、私たちは以下の指標を設定している:
- 参加者数の推移(年間目標:500名)
- 水泳技能習得率(基本的な浮き身・25m泳法完成率)
- 地域コミュニティとの連携数(保育園・学校との協力関係)
これらの数値を継続的に追跡し、改善を重ねていくことで、より多くの子どもたちに安全な水泳技術を届けていく計画だ。

未来への提案と発信
今、私たちに求められているのは、単なる事業拡大ではない。一人でも多くの子どもの命を救うという使命感を持った取り組みである。
日本企業が海外展開を考える際、往々にして「利益」が最優先される。しかし、真の国際貢献とは、現地の社会課題に真摯に向き合い、日本の強みを活かして解決策を提示することではないだろうか。
私たちの挑戦は始まったばかりだ。ベトナムで培った経験を基に、アジア全域に「泳げない子をゼロに」の輪を広げていく。そして、いつの日か「アジアの子どもたちが水難事故で命を落とすことがない世界」を実現したい。
あなたもこの挑戦に参加してみませんか。技術や資金だけでなく、一人ひとりの想いが集まることで、大きな変化を生み出すことができるはずです。

◇鮎澤 貴孝(あゆさわ たかのり)
株式会社エスアンドエフ 事業本部長 / ベトナム現地法人S&F VIETNAM 代表
新卒でサギヌマスイミングクラブを運営する株式会社エス&エフに入社。スイミングクラブ事業部でスイミングコーチをしながら、イベントの企画・運営に従事。サギヌマスイミングクラブ鷺沼の支配人を務めた後、マーケティング事業部でスイミングクラブ事業部のマーケティング業務全般を担当。2019年8月からはS&F VIETNAMの代表として、ベトナムに駐在。現在は、ベトナムで展開しているFuji Swimming Clubのコーチ育成や日本式スイミングクラブ運営の管理を担当。また、ベトナムの水泳普及に向け、水泳に関する動画をYouTubeで配信する。